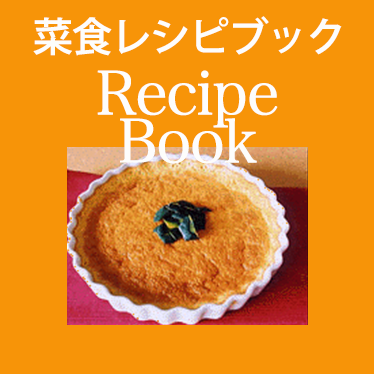食の安全安心は、食品ラベルを知ることから
名称、原材料名、賞味期限や消費期限、内容量、保存方法、販売者……。これらは食品に必ず表示しなければならない情報ですが、この他にも原産地や、遺伝子組み換え作物を使っているかどうか、農薬の使用状況など、食品表示の内容は多岐にわたります。そのため、知りたいことがたくさんあるけど情報が多すぎてわからないという人も多いはず。
食品の安全基準をはかるうえで大切なこれらの情報を、いかにして正確に読み、判断していけばいいのか。安全で環境にやさしい食品を提供する宅配会社「らでぃっしゅぼーや」にその秘訣を聞きました。
高まる「食の安心・安全」志向
21世紀に入りBSE(牛海綿状脳症:通称「狂牛病」)問題、2007年は食品表示や産地の偽装、2008年は中国産のギョウザに農薬が入っていた事件など、近年、食の根本を揺るがす事件が相次いでいます。その影響からか「安心・安全」な食材に対する志向が高まりを見せています。
有機・低農薬農産物の流通・消費を国内で広げるために1998年に立ち上がった食品の宅配会社「らでぃっしゅぼーや」は、全国の農家や食品業者と直接契約を結び、農作物の栽培期間中は極力農薬を使わない、加工食品にはなるべく添加物を使わないなど独自の厳しい基準を設けています。扱う食品は、バナナなど日本で栽培できないもの以外はほとんどが国産です。7000アイテムの中から毎週、旬の野菜や果物、肉や魚といった新鮮な食材がカタログに紹介され、それぞれの生鮮食品には産地、生産者名、農薬使用状況などの情報が細かい文字でぎっしり羅列されています。その他にも、「無」(らでぃっしゅぼーやの基準に沿って栽培された農作物:栽培期間中農薬使用なし)や「有機」(JAS法で認められた有機農産物、畜産物)、「非遺伝子組換」(畜産物の肥育期間中、遺伝子組み換えの可能性のある作物は飼料に使用していないもの)、「産直」(産地やメーカーから直送)、「回収」(容器を回収する)などのマークがつけられています。
そんならでぃっしゅぼーやでさえも、最近は、次のような問い合わせや声が増えているようです。
「パッケージに小さな傷がついているんだけど、大丈夫?」
「商品カタログにすべての原材料の原産地を表示してほしい」
「らでぃっしゅぼーやで扱っている商品には中国産の食材がないから、いつも安心して食べられる。加入していてよかった……」
消費者がいかに「食の安全・安心」に対して敏感に反応しているかがわかります。
食品にはどんな表示の種類があるの?
自分の目で食品の安全を確認し、判断するには、食品ラベルを読み解くための基礎知識が必要です。ところが、食品表示には「食品衛生法」や「JAS法(農林物質の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)」、「景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法:虚偽や誇大表示を禁止する法律)」の他に、「計量法」「健康増進法」「薬事法」といった複数の法律が関わっており、複雑でわかりにくい。しかも、それだけではなく「有機JASマーク」や容器包装の「資源回収マーク」、「トクホ(特定保健用食品)マーク」など、食品の容器にはさまざまな情報が踊っています。なかには、「コラーゲンたっぷり」「コレステロールを2分の1カット」といったキャッチコピーもあり、あまりにも情報が多く、「食品表示はわかりにくい」とサジを投げたくなる人もいるのではないでしょうか。そこで、食品の表示にはどんな情報があるのかというところから見ていきましょう。
食品の容器包装には、必ず次の項目が記載されているはずです。これらがまずは基本の情報になります。
・ 名称
・ 原材料名
・ 賞味期限または消費期限
・ 内容量
・ 保存方法
・ 販売者(製造者)

会員制のスーパーマーケットから、毎日大量の食料を引き取る。十分新鮮で、美味しく食べられる素材ばかり。
原材料名は、すべての食材(食品添加物を含む)を使用量の多い順に表示します。加工食品の場合、食品添加物を使うためどうしても情報量が多くなりがちです。食品添加物には、調味料、pH調整剤、増粘剤、酸化防止剤、着色料などがあり、それら一つひとつについても「調味料(アミノ酸等)」などと記載しなければなりません。
また、産地偽装事件の影響もあり、主要な原材料名に原産地を表示する流れも加速しています。2008年8月には東京都が調理冷凍食品に対して原料原産地表示を義務づける条例を公布しました。この動きは今後、国内に大きく広がることが予想されます。
賞味期限、消費期限は、いずれも未開封の状態で定められた保存方法の通りに保存した場合に食べられる期限のことです。消費期限とは、生鮮食品など劣化が早い食品に表示され、期限を過ぎると安全性が損なわれる恐れがあるため、必ず期限内に消費すべき食品に表示されます。賞味期限は比較的劣化しにくい食品が対象で、安全性、風味などすべての品質が十分に維持されることが保証される期限のことです。
ここで大切なのは「定められた保存方法で」というところで、保存方法が適切でなければ、期限内であっても美味しく、安全に食べられるとは限りません。例えば冷蔵品を常温に放置しておけば必ず劣化します。
また、食品の品質を担保するうえで必須なのが、製造者、あるいは販売者の情報です。何か事故が起こったり、あるいはより詳しい情報が必要な場合、製造者に問い合わせができるようにしなければならないからです。
「安全」の基準は個人の価値観によって違う
そもそも食品表示とは、一体何のために行われているのでしょうか?
食品表示の目的は、大きくは次の3つとなります。
(1) 健康危害を防止するための情報提供
……アレルギーの原因となる原材料の有無、保存温度、賞味期限など
(2) 食品選択のための情報提供
……食品の産地や原材料、栄養成分など
(3) 食品に対する優良誤認の防止
……栽培方法(有機、無農薬等)など

らでぃっしゅぼーや
田中早希子さん
「食品表示で何を重視するのかは、選ぶ人の価値観によって大きく異なるのではないでしょうか」
こう話すのは、らでぃっしゅぼーやのコーポレート・コミュニケーション室でプランナーを務める田中早希子さんです。例えば、農薬の使用状況が気になる人は有機JASマークや特別栽培などの表示を中心にチェックするでしょうし、遺伝子組み換え作物を絶対に採りたくない人、添加物を極力減らしたい人など、人によって「安心・安全」の基準は異なるからです。
特に、子どもにアレルギーがある場合は、食品表示の情報が重要な判断基準となります。アレルギーの原因となる原材料の表示については、社会通念上誰もがわかる表現であることが求められます。
食材によっても、必要な知識は異なってきます。野菜や果物などの農作物は、農薬や化学肥料の使用状況や産地などが重要視されますし、海外から輸入する柑橘類などは、防かび剤の使用状況が気になるところです。畜産物もさまざまで、牛乳ならば生乳か加工乳か、あるいは殺菌温度の違い。肉であれば品種や産地、こだわっているところであれば飼料の情報も追加されます。水産物の場合は産地や冷凍状況、養殖かどうかなどが表示されますし、加工食品は原材料や添加物など使用する材料が多くなるため、それに伴い文字情報も多くなりがちです。
また、容器包装のごみのリサイクルのための「プラマーク」や「紙マーク」なども、これからはますます注目されることになるでしょう。
いずれにせよ、すべての表示を読み解くことはなかなか難しいのですが、「国産であること」「添加物が少ないこと」など、自分が何を重視するのかを決め、自分なりの判断基準を設けて表示を読む必要があります。今は、食品表示に関する書籍もいろいろ出ていますし、生協などではリーフレットを配っているところもありますので、一度目を通しておくとよいのではないでしょうか。
これだけは知っておきたい食品マーク
 | JAS:
品質、成分、性能等がJAS規格(日本農林規格)に適合している製品(食品や飲料品、林産物)に表示 |
 | 有機JAS:
有機JAS規格を満たす農産物(有機農産物、有機農産物加工品、有機畜産物)などに表示 |
 | HACCP:
厚生労働大臣より承認された「総合衛生管理過程(HACCPシステム)」が満たされた工場等で製造された食品に表示 |
 | トクホ:
厚生労働省が健康の維持・増進と病気の予防に役立つ食品に、具体的な健康表示を許可した特定保健用食品に表示 |
 | 特別用途食品:
乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用等、特別の用途の食品に表示(厚生労働省が許可) |
 | 特別栽培農産物:地域の慣行栽培レベルの農産物より、節減対象農薬の使用回数と化学肥料の窒素成分量が50%以下で栽培された農産物に表示
|
 | 公正マーク:
公正取引協議会の公正競争規約によって製造、販売される商品に表示
|
 | マリンエコラベル:
日本水産資源保護協会が認定した、水産資源や海洋環境に配慮して収穫された水産物に表示 |
 | リサイクル表示識別マーク:
製品の廃棄時に資源として再使用するために、紙、ペットボトル、アルミ缶、スチール缶などに表示する識別マーク
|
| *その他、牛乳パックの再利用マーク、エコマーク、統一美化マーク、再生紙の古紙含有率表示、PETボトルリサイクルマーク、リサイクルプラスチックマークなど容器リサイクル関連のマークは多岐にわたる
|














 環境危機で変わる子どもの生活
環境危機で変わる子どもの生活