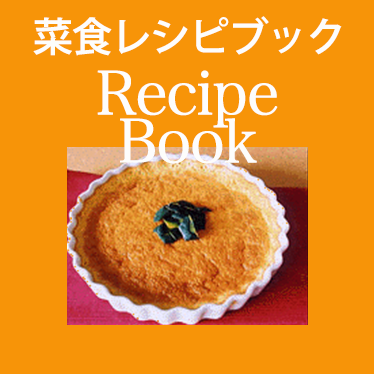地球にも家族にもやさしい食品選びのコツ
食品表示制度は法律が多岐にわたり、とても複雑でわかりにくいものです。しかし、自分なりの価値判断基準を持っていれば、意外と簡単に食材を選ぶことができるようになるかもしれません。そして、私たちの消費のあり方が変われば、日本の食品流通全体が大きく変化する可能性があります。
今、なぜ食料の宅配が注目されているのか?

らでぃっしゅぼーや
益貴大さん
らでぃっしゅぼーやは現在、約9万5000世帯の加入者がおり、特に最近は若い世代の加入が相次いでいます。ターゲットは、加入者の約半数を占める30〜40代のファミリー層。
「子どもに、家族に安心して食べられるものを与えたい、という思いが加入の主な動機のようです」。こう話すのは、らでぃっしゅぼーやコーポレート・コミュニケーション室で広報を担当する益貴大さんです。
こうした宅配サービスは、妊娠した、子どもが生まれた、子どもに何らかのアレルギーがあるなど、子どもに安心して食べられるものをという「安全志向」を満たすこともさることながら、お米やミネラルウォーターといった重いものや、トイレットペーパーや洗剤などの日用品を玄関先まで運んでもらえる「利便性」を両立するサービスと言え、買い物よりも育児の時間を優先したいという親のニーズに合致していると言えます。

らでぃっしゅぼーやの宅配
らでぃっしゅぼーやに限らず、生協を含めた食品の宅配事業では、それぞれの組織ごとに独自の基準を設けているところがほとんどで、その基準こそが事業の理念と言うことができます。らでぃっしゅぼーやの場合は、「環境保全型農産物の提供」「徹底した情報公開」「先進的な商品開発力」を軸にしており、食材はほぼ国産、農薬をなるべく使わない、添加物は必要がないので最低限しか使わないという考え方が、すべての商品で徹底されています。
このように、「この宅配事業者(生協)を選べば、最低限これだけの安全を得られる」という判断も、食品を選ぶ一つの基準と言えるのではないでしょうか。
このように、「この宅配事業者(生協)を選べば、最低限これだけの安全を得られる」という判断も、食品を選ぶ一つの基準と言えるのではないでしょうか。それプラスアルファとして、店舗でも購入したい、社会的な運動を展開したい、地域で仲間をつくりたい、なるべく手間なく簡単に食材を得たいなど、自分の生活スタイルやニーズに合わせて事業者を選ぶとよいでしょう。
有機農産物を食べることは、地球にやさしい行動
らでぃっしゅぼーやは1977年から20年に渡って活動していた環境NPO「日本リサイクル運動市民の会」が母体となり、「有機・低農薬農産物の生産・消費の輪を広めることは、環境保全活動の一環である」という理念のもと、1988年に会員制宅配事業をスタートしました。

らでぃっしゅぼーやの契約生産者、笑顔が誇らしい
有機農産物とは、原則として農薬や化学肥料を使わず、種まきや植付けの段階から遡って2年以上(あるいは3年以上)、禁止されている農薬や化学肥料を使用していない田んぼや畑で栽培されている作物のことを指します。これらは、生産から出荷までの生産工程や数量の記録を作成し、いつ、誰が、どのように生産し、流通しているのかを追跡できるようにしなければなりません(トレーサビリティ)。これらを国が定めた登録認定機関が認証することで、「有機JAS」と認定された食品になります。
ところが、日本の有機農産物の流通規模は、日本の食品流通全体ではわずかに0.19%に過ぎません。これだけ安全志向が高まっているにも関わらず、です。
これは、有機JAS制度はヨーロッパの基準がもとになっているため、高温多湿・耕作面積が狭い等、栽培条件が異なる日本では、実際に認証を受けられる農家が少ないためです。らでぃっしゅぼーやなどの自然食品宅配業者では、できるだけ農薬や化学肥料を使わない農家がやっていけるよう独自基準を設け、これに基づいて管理しています。
「国内で持続可能な農業を推進するということは、自給率の向上にもつながります。実は国産の食材の方が、トレーサビリティがはっきりしているので、食品業者にとっては管理しやすい、というメリットもあります」と、益さんは打ち明けます。
また、田中さんは「私たちが食品を食べるということは、それをつくってくれる人がいるということ。いのちあるものを適切な価格で購入し、残さず大切に使うという食行動が、日本の農業の市場を広げていくことにつながるのではないでしょうか」と話します。
2006年には40%を割って39%に落ち込んだ日本の食料自給率は、2007年にはわずかながら回復(40%)したことには、希望を持ってもいいかもしれません。まずは国内で農業に携わる生産者の働きが金銭面で評価され、日本の農業が元気になること。それから少しずつ農薬を減らし、田畑の環境を守ること。それが未来世代に持続可能な社会を残すという意味でも、重要な指標になるはずです。
地場産の食材に注目すれば、地球も、地域も元気になる
らでぃっしゅぼーやには、「いと愛づらし(めづらし)名菜百選」というユニークな企画があります。日本各地で受け継がれてきた伝統野菜は、栽培が難しかったり、使いにくいという理由で市場から急速に姿を消しつつあります。こういった野菜を取り扱うことで、伝統野菜と、その地域で育まれてきた食文化を未来につないでいこうというのが目的です。例えば「雲仙こぶ高菜」は、ゴツゴツしたこぶが特徴の見た目にもひょうきんな葉物で、らでぃっしゅぼーやの取り組みから火がつき、2008年7月にはイタリアのスローフード協会国際本部から日本で唯一のスローフードの最高位「プレシディオ」に認定されるまでの名産品に成長しました。地域の食材と文化の関わりに注目することで、地域おこしにつながった好事例と言えます。

いと愛づらし(めづらし)名菜百選

雲仙こぶ高菜

取材協力
らでぃっしゅぼーやには、「いと愛づらし(めづらし)名菜百選」というユニークな企画があります。日本各地で受け継がれてきた伝統野菜は、栽培が難しかったり、使いにくいという理由で市場から急速に姿を消しつつあります。こういった野菜を取り扱うことで、伝統野菜と、その地域で育まれてきた食文化を未来につないでいこうというのが目的です。例えば「雲仙こぶ高菜」は、ゴツゴツしたこぶが特徴の見た目にもひょうきんな葉物で、らでぃっしゅぼーやの取り組みから火がつき、2008年7月にはイタリアのスローフード協会国際本部から日本で唯一のスローフードの最高位「プレシディオ」に認定されるまでの名産品に成長しました。地域の食材と文化の関わりに注目することで、地域おこしにつながった好事例と言えます。
こういった地場の食材探しは誰にだってできることです。地元の産地直売所や農協の店舗、各地の道の駅などに足を運べば、その土地ならではの野菜や果物などが目に入るはずです。たいていは朝採りの新鮮なものばかりで、少量、多品種が売りです。「食品表示」の面からすると情報は十分とは言えませんが、こういったところでは生産者が直接販売をするため、農薬の使用状況などが気になるなら直接聞いてみるのもいいかもしれません。
益さんと田中さんは、今、若い人やリタイア世代が「土に還っている」実感がある、と言います。実際にらでぃっしゅぼーやの生産者でも、後継者が育ちつつあり、また、新たに農業に従事する人が増えてきているそうです。
「未来はそんなに暗くない、と私たちは考えています。食品を買う時、ちょっと考えて選ぶこと。それがつくる人を応援することにつながり、日本の食卓と地域の文化が元気になっていくはずです」(益さん)
「選ぶ」「買う」から始める「地球にやさしい食生活」。自分の基準を持って、食品表示にちょっとだけ気を配ることが、その第一歩になるはずです。








 環境危機で変わる子どもの生活
環境危機で変わる子どもの生活