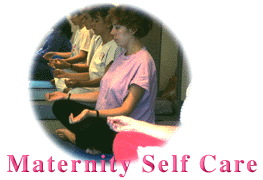産みの場
産みの場は産小屋から、次第に自宅へと移り、さらに現代は医療施設へと、またまた自宅外へ移行している。
産小屋から自宅へ移行したと言っても、もちろん昔むかしのその昔から自宅で出産していた人々はたくさんいたし、産小屋があった時代でも、自宅で出産していた人々はたくさんいたと推測される。産小屋というのは、お産にまつわる文化なのだから、ところ変われば、また身分によってもその文化は様々だったろう。
自宅に移ったお産も、すぐに畳の上というわけにはいかなかった。始めのうちは、土間が産婦に与えられ、やっと座敷に上がったと思っても、納戸や一番奥まった部屋で出産は行われた。これも、不浄感によるものと、実際的に血液が飛ぶなど汚れることへの対処方法だったようだ。
しかし、土間にも納戸にもそこに込められた意味がある。土間には、カマドがあり、カマドの前で出産したり、また地炉(ヂイロ)といって火を燃やす道具が用意されその傍らで出産した地方もある。これは、火によって産婦や赤ちゃんを暖めるという意味と、火の神の守護を得るという信仰もある。東南アジアでは、産後、母親を火であぶる習慣が今も残っている地域があり、これは火を焚くことによって、邪気を払うというものと、不浄を清めるという意味があって、火は絶やさず数日間焚かれる。
また、納戸は穀物や家財の大切なものをしまっておくところでもあり、穀物には穀物の霊がやどるとされ、女たちはそれを納戸神として奉ってきた。納戸の稲が発芽し、成長するのは、稲にある魂(エネルギー)が充実するからだと考え、それにあやかって人の子の魂も母の子宮にこもり、成長して誕生することができると昔の人は考えていたという説もある。
また、納戸や産小屋が静かで暗い部屋であったことは、静けさや暗がりが生まれてくる赤ちゃんにとって必要だったことを経験的に知っていたからだろう。現在は、科学的に生まれたばかりの赤ちゃんがとても敏感で感受性が強いことがわかってきて、分娩室には暗く静かな環境が求められてきている。
さて、1950年代に日本のお産は自宅から医療施設へと完全に移行した。その意味は?と考えると、いくつか考えられる。ひとつには、出産は医療に守られるべきという考えが一般的になったからだが、これは科学信仰といってもいいかもしれない。分娩室を隔離し、病原菌から守る。あるいは、難産を外科的に処置する。こうしたことは、多くの人々を不幸から救ったために、医学はまるで救世主のごとく崇め奉られるようになった。しかし、かつての神の守護は失われてしまっている。
また、自宅で出産が行われるようになった時代は、家には多くの家族がいて、嫁はその中であまり快適な立場にはいなかった。姑などに気がねをし、なかばイジメのような扱いを受けた女たちも多くいる。
そうしたことからも、家のソトに出て出産するということは、女たちにとって現実からの逃避として意味があったのではないだろうか。あるいは逆に核家族になり、お産の手助けをしてくれる人がいなくなったことから、専門家にそれをゆだねるようにもなった。
しかし、またまた時代は変遷している。これからのお産は、はたしてどこにゆくのだろう?
参考文献/『日本人の子産み・子育て--いま・むかし』鎌田久子ほか著/勁草書房
文/きくちさかえ 掲載:1996年 更新:1999年
babycom おすすめ関連コンテンツ