あたたかいお産と子育て NICU編
シリーズ『あたたかいお産と子育て』では、葛飾赤十字産院院長、進 純郎先生に産科についてのお話をこれまでうかがってきました。今回は、生まれたばかりの赤ちゃん、しかもNICU(新生児集中治療室)に入院している赤ちゃんについて、同病院の小児科部長、島義雄先生にお話をお聞きしました。
島 義雄 先生(掲載当時:葛飾赤十字産院 小児科部長)
生まれたばかりの赤ちゃんの中には、さまざまな原因で治療を必要とする赤ちゃんがいます。そうした中には、小さく生まれた赤ちゃんもいます。
小さく生まれた赤ちゃんには、出産予定日までおなかの中で育つことができずに早い週数で生まれてしまうケースと、おなかの中には十分いたけれどもなんらかの原因で十分に育っていないケースとがあります。前者は早産で生まれた赤ちゃんで、いわゆる未熟児と呼ばれています。後者の低出生体重児は、母親の妊娠中毒症や合併症などや、赤ちゃん自身に染色体異常や病気がある場合などがあります。
NICUには小さく生まれた赤ちゃんのほかに、病気をもった赤ちゃんたちもいます。原因はさまざまですが、生まれつき病気をもっている場合もありますし、お産そのものが赤ちゃんにとって大変なストレスとなり、誕生後、外の環境に順応するためのスイッチがうまく入らない、いわゆる仮死で生まれてきた赤ちゃんもいます。
NICUにる赤ちゃんたちは、生まれたときには大きい子もいれば小さい子もいるのに、みんな同級生になるわけです。そうした赤ちゃんを集中的に管理し、治療を行なっています。
日本の場合、法律的には22週未満が流産、22週0日から早産と定められています。生育限界という言葉がありますが、生物学的に育つことができる限界の週数は、法律上では22週ですが、実際には生まれてくる赤ちゃんが半分以上育つ確率が出てくるのは24週を越えてから。25週を越えるとその確率は急に上がり、全体の8割以上の赤ちゃんが育つようになってきました。テクノロジーが進むにつれて、その確率がここまで高まってきたのです。
大きさについて言えば、500g未満の赤ちゃんが少しずつですが育つようになってきました。けれど、500g未満の子がすべて育つということではなく、可能性が出てきたということに過ぎません。
現在の新生児医療は、テクノロジーの発達と研究の努力の成果により、昔よりはるかにたくさんの赤ちゃんを助けられるようになりました。それによって、生育限界も下がってきていますが、それは何百gの子を助けることができるというレコードをつくる競争ではなく、なんとか助けたいという努力をしているうちに、結果的に現在の数字になってきたということなのです。
生育限界が下がってきたことによって、昔だったら助からなかった28〜30週の赤ちゃんや後遺症が残ったケースが、今は後遺症もなくほとんど普通の子と同じように育つようになってきました。しかし、生育限界がさらに下がっていくとは思えませんし、できるだけ長くおなかの中にいるほうがいいというのは、当然のことです。
小さく生まれる赤ちゃんは、増える傾向にあります。その原因のひとつに、不妊治療による双子、三つ子の増加が上げられます。多胎はおなかの中に赤ちゃんが複数入っているわけですから、小さく生まれる確率は当然高くなります。もちろんそれ以外にも、さまざまな要因があります。
NICUというのは、赤ちゃんのICU(集中管理治療室)のことで、新生児科のある大きな病院に備わっています。部屋は細菌などの感染を予防するために厳重に管理され、赤ちゃんたちはひとりづつ保育器の中で、酸素や栄養をもらいながら治療します。
NICUのある病院は限られているので、その他の病院や産院からも多くの赤ちゃんが送られてきます。自治体によって、NICUのある病院の数はそれぞれですが、東京のように同じくらいの規模のNICUをもつ病院が相互にネットワークしている地域もあり、都内にはそうした病院が20件ほどあります。しかし、県によってはその整備が不十分な地域もあり、厚生労働省などでは各県に十分な配備ができるように準備をしているところです。
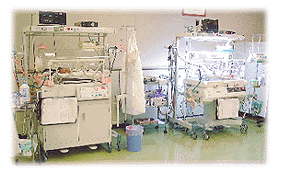
NICUのニーズは年々ひじょうに増えてきていて、東京では定員いっぱいの施設がたくさんあります。そうしたことから、NIUCをもつ病院がネットワークをつくり、どこの病院のベッドが空いているのかなど情報を交換し、対応できるようにしています。
NICUには、周辺地域から赤ちゃんたちが搬送されてきます。ですから、そうした施設は地域の中でセンター的な役割を果たしていることになります。ときには、近くに病院がなかったり、たとえあったとしてもベッドが空いていない場合には、かなりの遠距離から搬送されてくる場合もあります。ここ10年で、送られてくる赤ちゃんの数は増えてきています。
生まれたばかりの赤ちゃんに何らかの問題が起きて、搬送されてくる場合もありますが、未熟児の場合は母体搬送といって、出産する前に母親ごと紹介されて転院してくるケースがほとんどです。超音波診断によって、生まれてすぐに手術が必要なケースや、特別な治療が必要なケース、また週数の割に小さいということなども、胎児の段階でわかるようになってきました。とはいえ、超音波のビジュアルでは見えない機能的な病気もありますから、すべて超音波で発見できるというわけではありません。
搬送時期は母親の容態や状況によってさまざまです。赤ちゃんに問題がある可能性が高い場合には、出産がさらにストレスになることもありますし、いつ早産になるかわからないという危険性も含んでいるので、NICUのある施設にあらかじめ入院して待機します。そうすることによって、出産後すぐに新生児科の医師が赤ちゃんを診ることができます。
出産はケースバイケースですが、医師の判断を母親と家族に十分に説明した上で、ベストな方法が選択されます。場合によっては、帝王切開になることもあります。
早く生まれた早産児と、早産ではないけれども病気をもった赤ちゃんとでは、治療の方法は異なってきます。
早産で生まれた小さい赤ちゃんの場合には、本来安全であったはずのおなかの中の環境を再現してあげるということが治療の要点になります。おなかの中では息を吸ったり吐いたりしていませんが、生まれてきた以上は呼吸をしなければいけません。100%おなかの中と同じ環境にすることはできませんが、保育器の中の温度や湿度を子宮の中と同じように保ちます。呼吸する力が弱く、酸素をとり入れにくい場合には、人工呼吸器をつけることになります。自分の力で母乳を消化することができない場合には、チューブで栄養を与えることもあります。
からだに、いろいろな機械がいっぱいつながれることになりますが、機械で生かされているというわけではなく、機械の力を借りておなかの中の環境を再現しているのです。早産児の場合には、こうした人工的な手助けをしながら、さらに時間の経過が必要になります。
早産ではないけれども、仮死で生まれたり、羊水を吸い込んでしまったり、外の環境になかなか適応できないケースもあります。内臓の機能はある程度できていますが、こうした場合も、子宮に近い環境をつくることで環境の変化の橋渡しをしてあげます。
おなかの中にいれば100%健康な赤ちゃんでも、おなかの外にいるということ自体が重大事。心臓の疾患など、病気をもっている赤ちゃんもいますし、さらにそうした病的な赤ちゃんが早産で生まれてくることもありえるのです 。
治療は、その赤ちゃんにあわせて行なわれます。人工呼吸器が必要なのか、ばい菌をやっつける抗生物質を使うのか、免疫を助ける物質を注射する必要があるのか。それを見極め、それぞれにサポートしていくかということが、NICUの治療です。


 妊娠・出産・産後ワード101
妊娠・出産・産後ワード101 ベビーマッサージ
ベビーマッサージ 子どものための快適空気環境
子どものための快適空気環境