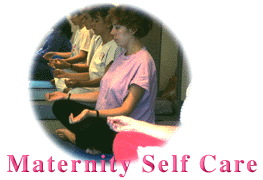World report Tibet
チベット Part2「納屋で産んだ母親」
首都ラサから車で3時間ほど行った、小さな村を訪れました。そこで1ケ月前に出産したという女性に会いました。彼女はなんと、家の庭にある納屋で出産したというのです。3人目のお子さんですが、お産のとき夫は半年間の遊牧生活に出ていて留守。日本で言えば、長期出張中というところでしょうか。
お産は産婦の母親が付き添ったそうです。3日間陣痛が続き、3日目の朝、彼女は家の中にいたのですが、突然外に出たくなり、納屋へ行ったといいます。チベットの遊牧民たちの多くは、ヤクという動物を飼っています。一家に少なくとも一頭はヤクがいる。そのヤクから、ミルクや毛皮をとるわけです。
彼女は、そのヤクの小屋へ行きました。そこに地面に少し高く藁が積み上げられていました。女性はとっさの判断で、どこに赤ちゃんを産めばいいのか判断するようです。外で産む場合も、赤ちゃんを産み落とす場所を直感的に見つけます。どこで産んでもいいというわけではないのです。もちろんこうしたことはマニュアルがあるわけではありません。だれかが指し示したわけでもありません。
とにかく彼女は、藁の山をみつけ、その藁をまたぐ格好で、立って出産したと言いました。「子どもが出るとき、思わず前へぴょんと飛んで、赤ちゃんはおしりのうしろに出てきた。ははは」と言って、笑いました。産婦の母親が、とっさに藁の山の上で赤ちゃんをすくい止めた形になったそうです。
●胎盤に感謝し、神の川へお返しする
その女性に「医師も助産婦もいないこの土地で、ひとりで出産するのはこわくなかったですか?」と、私は質問しました。すると、その女性は驚いたような表情をしました。そして「あなたはお子さんがいますか?」と聞くのです。「はい」と答えると、彼女はさらに不思議そうな顔をします。なんで、この女(私のこと)は、自分で産んだことがあるのに、そんなことを質問するのか、といった表情です。
そして、「お産は女の仕事。なんでこわいのですか?」と言いました。
この村の人たちは、現在でも全員が自宅で生まれています。ほとんどみんな健康で元気なお産だということでした。
「でも、死んだ赤ちゃんはいないんですか?」とさらに私はたずねました。
すると、「そりゃあ、まれには死ぬこともある」と。それはほんとうに自然に出た言葉でした。そこにはなんの悲愴感もただよってはいませんでした。「まあ、いろいろなことはある。でも、それを恐れず、受け入れているのさ」と言っているように聞こえました。
その言葉は、おおげさに言えば、私のお産感、人生感を変えたと言ってもいいかもしれません。もちろん、それを今の日本の医療とくらべることはできません。しかし、チベットという国は、位の高いお坊さんは、今でも鳥葬をしています。鳥葬の場合は、村のはずれに鳥葬台が設けられ、そこに死体がさらけ出されるのです。生も死も生身のまま、人々の目の前にさらけ出されている。死は敗北ではなく、自然の中の一部で、自分の生ととなりあわせにあるものだと、チベットの人たちは考えているのかもしれません。ひじょうに過酷な自然条件の中だからこそ、死と生を、あるがままに受け入れることができるのかもしれません。
ちなみに、産後、胎盤はどうするのかと質問したところ、川へ返すという答えでした。チベットの川は、日本の河川とは違います。日本で今、胎盤を川に捨てたら大変なことになりますが、チベットの川は、ヒマラヤの雪解けの水をたたえた神聖な川です。人々は、その川の水を飲んで暮らしています。その川へ流すのです。それは、川へ捨てるという行為ではなく、10ケ月間子どもを守ってくれた胎盤に感謝し、神の川へお返しするという人々の願いがこめられているのです。
世界各地で、私は胎盤の処置の仕方を聞いてきましたが、川へ流すという話を聞いたのは、チベットと戦前の東北地方だけです。
2003年7月 きくちさかえ記