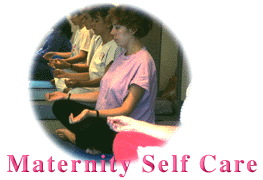助産婦の戦後の歴史
助産婦という職業は、それこそ昔は、たいへんなものだった。
産婆が職業として確率されてから、村でかしこい女の子は「何か手に職を」と考えて、産婆になったという話はよく聞く。村でも町でも、産婆たちはキチッと着物の襟を立て、あるいはしゃれた洋装で、人力車や自転車に乗って、産婦の家を回っていた。一般家庭に電話のない時分に、産婆の家には電話があった。女性が専門職につくことがあまりなかった頃から、彼女たちはキャリアウーマンだったのだ。
“産婆”という言葉は正式には、200年ほど前に中国から伝えられたのだそうだ。もちろんもっと古くから“とりあげ婆さん”“へそ婆”などと呼ばれていたのだが、昔はこの“婆”という言葉には、尊敬の念が込められていたのではないかという説もある。先住民族などが俗に言う“長老”といった、目上の智恵のある人にたいする名称が“婆”だったというのだ。
その“産婆”が、“助産婦”に変わったのは、1947年(昭和22年)。“婆”という字が、おばあさんを思わせるので古くさいから変わったという説もあるが、実際は、戦後のアメリカの占領下で、看護職の法律ができたときに、名称も今風にと変化したものだ。
敗戦後。負けた国、そして先進国ではなかった日本をたて直そうと、アメリカはGHQ(連合国最高司令官総司令部)を日本に派遣してきた。そのGHQの政策に、日本の産婆たちはそれまでの伝統を大変革させられる危機に迫られてしまうことになる。
興味深いことに、憲法が制定されるのとほぼ同時期に、産婆は助産婦へと改名されている。日本に“助産婦”が誕生したのが47年5月1日、その二日後の、5月3日が『憲法記念日』の初日である。
すでにご存じのとおり、この当時のアメリカのお産は、病院での麻酔分娩が主流。助産婦はいなかのほうの移民のお産に登場するくらいのもので、「出産の将来はわが手にあり」と産科医たちは左ウチワ状態。助産婦は、消え入る寸前のカゲロウみたいな存在だった。助産婦の社会的地位が低かったそんな国が、手本になろうというのだから、日本の産婆はたまったものではない。不幸はここから始まった。
まず、GHQの公衆衛生福祉局の女性担当官がやってきて「助産婦は、看護婦、保健婦と同じ看護関係者ですね」と、三つの職種を簡単にまとめてしまった。実はこの女性、なんと看護婦で保健婦 。日本の助産婦のことはもちろん、助産婦そのものに対する理解に欠けていたのだろうと想像できる、その職歴である。
「三つの看護職をまとめた協会をつくろうと思うの。そういうわけで、産婆さんたち悪いんだけど、日本産婆会を解散してくれないかしら」
さあ、これは大変。当時、日本の赤ちゃんの九割が自宅で生まれていたのだから、それを一手に握っていた産婆たちの勢力は、看護婦よりずっと強かった。日本産婆会は大騒ぎになった。
しかし戦争に負けた弱み、結局、助産婦、看護婦、保健婦はそれぞれの協会が統合され、「保健婦助産婦看護婦法案(保助看法)」と呼ばれる法律がつくられた。このときから、産婆という特殊技能をもった職業は、日本の中でも看護の領域に入れられてしまったのだ。
それまで、産婆は、産婆としての独自の教育を受けていたのだけれど、その法律では、まず三年間の看護教育をみっちり受けた上で、さらに助産婦としての教育を受けられるとされた。それ以降、教育を受けた助産婦たちは、みんな看護婦の資格をもつことになる。
保助看法ができた頃、日本は戦後のベビーブーム。そのベビーブームを支えたのは、ほかならぬ名前も新たな助産婦たちだった。くる日も、くる日も、産婦の家を回って、寝る暇もなかったと、この頃開業していた助産婦たちは口を揃えて言っている。
よく働いたおかげで、彼女たちの中には、その後、勲章をもらった方々もたくさんいる。
しかし、これが実は、静けさの前の最後の嵐になろうとは、助産婦たちは想像していなかった。
その後、十年もたたないうちに、日本の出産は、施設へと移ってしまう。
自宅出産はみるみる少なくなって、開業助産婦は高齢化して先細りになるし、若い助産婦たちは病院などの施設に就職するようになっていった。病院では、定めのように医師の下で働くポジション。助産婦のアイデンティティーは揺らいでいったのだ。
でもまあ、こうした流れは、お産にどんどん欧米の産科学を取り入れようとしていた時代の中にあっては、遅かれ早かれ直面しなければならない問題だったのだろう。
文/きくちさかえ 掲載:1996年 更新:1999年